
企画・アイデアの沼にハマって残業続き……。Webディレクターはどう対処する?
はじめに
クリエイターに特化したビジネス書があってもいいじゃないか――。
仕事に関わる技術やキャリアだけでなく、疲れが取れる休み方、遊び方などの体調管理など。人生を効率的に・豊かに過ごすための「生活術」や「仕事術」をクリエイターの実例を通じてお伝えしていきます。
【執筆者】
Webディレクター・SEOエンジニア・マーケター・薬事法管理者
赤羽根 長子
2005年、30歳を過ぎ自分のスキルに不安を感じ、職業訓練校にて1年間プロクラムを学ぶ。2006年にWebディレクターに転身して健康美容業界の大型BtoBマッチングサイトの立ち上げメンバーとして参画。同年には薬事法管理者の資格を取得した。この時期よりSEOを体験的に学び、「無添加」「美白」「サプリメント」などのビッグワードで運用するポータルサイトを1位にまで押し上げる。2021年10月、編集プロダクション・ジュエルコミュニケーションズを設立。代表取締役に就任。

(株式会社ジュエルコミュニケーションズ代表)
Webディレクターは、時にプランナーとしてサイトやコンテンツ制作における企画・アイデア出しを求められます。
企画・アイデア出しで陥りがちなのが、煮詰まってしまったり、浮かんだアイデアが本当に良いのかわからなくなったりということ。一心不乱にアイデアをひねり出そうと試みたものの、ただ時間が過ぎていっただけ、という苦い経験をした人も多いかもしれません。
企画やアイデアは、ひたすらに時間を掛ければ良いというものでもありません。大切なのは、環境を整えたり、自分に合った手法を見つけたりすることです。
この記事では、おすすめの企画・アイデア出し方法を紹介したいと思います。いつもの発想法でなかなか上手くいっていないという方は、ぜひ一度試してみてください。
アイデアが降りてくるタイミングを掴む

企画が下りてくるタイミングを掴みましょう。企画やアイデアが閃く瞬間は、意外とデスクでパソコンの前に座っているとき以外だったりします。
それはお風呂に入っているときだったり、歩いているときだったりと、人によってシーンはさまざまですが、多くのプランニングに携わっていると、自分なりの「アイデアが降りてくるタイミング」が掴めてくるものです。
おすすめなのが「リラックスできる環境」
私の場合は、自分が一番リラックスできている状態に身を置くことを心がけていました。思考というのは“柔らかなところ”に降りてくるものです。そして自分だけの世界にどっぷりと浸かることが大切。思考力は半分、妄想力に近いんじゃないかなとも思っています。
オフィスのなかだと電話を取らなければならなかったり、上司から突然依頼が降りてきたりするのでなかなか集中できないことが多く、「ひとりだけの場所と時間を確保すること」が難しい……。
企画が煮詰まったら、私は定時で業務をさっと終わらせ、途中段階の企画書をプリントアウトして近くのバーに駆け込んでいました。
席がきちんと確保できて書類が広げられ、ゆったりとした時間が流れていて落ちつける場所――。それが私のなかでは近くのバーだったのです。
母子家庭で息子がまだ小学生だったため長くは滞在できませんでしたが、そこで一杯だけお酒を頼む。アルコールで少し温まった身体と脳で改めて企画書に目を通す。
社会人とも母親とも違う、自分だけの時間。
いつもと違う時間と景色。
静かに流れる音楽のなかで、新しいアイデアや気づきが降りてくることが多々ありました。
煮詰まったらいったん頭を休めること
よく「一晩寝かせる」という言葉を使いました。
つくった企画書やプランをいったん止めて、脳をリセットさせる。
そうすると、ちょっとした間違いや「ここをもっと膨らませたら面白いんじゃない?!」なんていう気づきがあったりするものです。
私が15年間活用しているアイデア発想手法

ここで私がおすすめする1冊の本を紹介したいと思います。
『考具(こうぐ)』(加藤昌治 著)という、アイデア出しの手法がまとめられたもので、面白く、多くの気づきを得られます。
発想を深く・広くしてくれる「マンダラチャート」
プロ野球の大谷翔平選手が使っていたことで一躍有名になった「マンダラチャート(マンダラート)」の存在を知ったのもこの本でした。大谷選手の場合は目標設定の方法としてマンダラチャートを活用されていましたが、アイデアなどの発想法においてもとても便利な手法です。
まず3×3の9マスを書き、「何についてのアイデアを出したいか」の主語に当たる部分を真ん中のマスに、そこから連想されるものを周囲のマスに埋めていきます。そのなかから「この言葉をもっと深堀していこう」と思ったものを、新しく用意した空白の9マスの真ん中に置き、再度周りの空欄を埋めて発想を深堀りしていきます。
この作業を繰り返すことで、今まで考えもつかなかったワードやアイデアが引き出されるのです。
ポイントは、浮かんでくる言葉が出なくなっても空欄をすべて埋めるということ。
脳に負荷をかけるこの作業が今までにないアイデアを生み出すきっかけになります。
アイデアのヒントを日常から探る「カラーバス」
また「カラーバス」という手法もおすすめです。
その日にまず注視したいカラーを1色決め、その色が目についたらその物がどんなアイデアや想い、手法でつくられているかを思考する。
例えば「青色のものに注目する!」と決めてから外出してみましょう。青色の看板、青色の表紙の本、青色の車などいろんなモノ・コトが目に入ってきて自然と思考が巡ります。
たったそれだけのことですが、日常のなかに潜んでいる、いつもは全く気にも留めなかったモノやコトに気づくことができます。これは今すぐにでもできるので、ぜひ試してみてください。
面白いくらい、世界にはいろいろなモノとアイデアで溢れているんだなと気づかされるはずです。
アイデアは思いもよらないところから降りてくるもの。
日常に刺激を感じながら過ごす、そうした気持ちが新しいきっかけを生み出してくれます。
プランニング現場に見る「傾向」と「対策」

思わずその世界にどっぷりと浸かってしまう「市場調査」
押し入れを整理しようと思って片付け始めたものの、気づけば開けた段ボールから出てきた懐かしいものたちに見入ってしまい、一向に片付けが進まない……。
そんな経験はありませんか? 例えると、「市場調査」とはそんな現場なのかもしれません。
【市場調査での傾向】
私が陥りがちな市場調査における「傾向」としてあるのが、その業界の魅力や面白さに思わず時間を忘れてどっぷりと浸かってしまうこと。
世の中のさまざまな商品やサービスは、売れているものこそそれだけの魅力があるものです。
そこに時間を掛けちゃいけないのはわかっているけれど、ついついネットサーフィンしたり業界本にまで手を出してしまったりすることも珍しくありません。
【対策】
そんなときの「対策」は、「そのプロダクトを売るには、このくらい“中の人”に近づくことが大切だよね」と開き直ることです。ワクワクしているところから良いアイデアは生まれるものです。決して自分を否定しないこと。ただし、掛けた時間分はきちんと自己回収しましょう。
パワーポイントで思わず出来上がりにうっとり「企画書づくり」
「これつくった人、天才じゃない?」
自分がつくり上げたパワーポイントの企画書に思わずうっとりすることってありませんか?
私は毎回そうです。でもきっと私だけじゃないはず。
【企画書づくり(パワーポイント)での傾向】
プレゼンや企画、営業資料が出来上がるたびに「うっとり」。
デザインもさることながら、大好きなフォントで綴られた文言に「うっとり」。
ちなみに、私はフォントではメイリオが大好きです。ほかの方がつくった資料も、フォントがゴシックだったりすると時間を掛けてでも全ページメイリオでつくり直すくらい、モチベーションを上げるのにメイリオを求めたりします。
ほかにも、パワーポイントでできる機能を最大限に活かしてみたくなったり、スライドを動かしてみたくなったりしてきます。
そうするとどんな弊害が起こるのか。
簡単に想像できるかもしれませんが、「残業」「睡眠不足」などに陥ります。そのほかにも、「デザインに凝りすぎて逆に見づらい」「ちょっと凝ったグラデーションを入れてみたら救いようがないくらいセンスが悪い」「そこまでつくり込んだのに、最後の制作費のページしか見てもらえない」なども起こりがちなマイナス点です。
【対策】
客観的に企画書を見てくれる同僚や上司に、途中段階でチェックやツッコミを入れてもらうことです。末期に陥る前に、第三者チェックを入れるなど「対策」しましょう。
ドラフトの段階でまずは第三者に見てもらうことは、アイデアが的を射ているものかを判断するのにも非常に重要な行程です。
見てもらうのは同僚でも上司でも良いですし、まったく仕事に関わりのない友人やパートナーでも良いでしょう。
企画書に初めて触れる人の意見は、クライアントの目線にも近く、何よりも貴重なアドバイスをもらえるものです。自分だけで満足しない、客観的に優れた企画を目指すには、できるだけ多くの人の目に触れてもらいましょう。
浮気をするのもひとつの手
私の場合ですが、煮詰まってアイデアが出てこないときにはすっぱりと諦めて、まったく別の業務に着手します。それはライティングの校正だったり、デザインディレクションだったりとさまざまです。
どれも仕事には変わりありませんが、別の業務をすると脳のストレッチにもなります。
アイデアはどんなきっかけとタイミングで降りてくるかわかりません。それであれば同じ場所にいてはもったいないし、同じ思考でいるのももったいない。
色々なモノとコトに触れ、脳を刺激する機会を増やしましょう。
企画やアイデアというものは、思いもよらないところで、思いもよらない形で浮かんでくるものなのです。
・・・
ーTwitter
はいふぁい@HIGH-FIVE転職エージェントでは「はいふぁい」編集部員が日常も交えて、クリエイターさんと遊んでいます(情報交換)。使える情報も3割!
ークリエイターキャリア支援メディア『HIGH-FIVE』
IT/Web領域クリエイターの転職情報・キャリアコラムを配信中!
1.C&R社の転職エージェントってなにしてくれるの?
2.具体的な転職事例が知りたい!
3.どんな求人を持っているの?
ーLINE
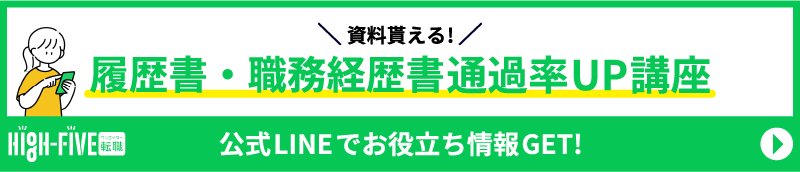
ーInstagram


